第20回 石西礁湖自然再生協議会を開催しました
平成29年2月19日(日)に、沖縄県立八重山商工高校において、「第20回 石西礁湖自然再生協議会」を開催しました。
協議会には、委員、傍聴を含め70名の方が出席しました。
 |
| 石西礁湖自然再生協議会の状況 |
はじめに、団体委員として「株式会社 エコー」の参加が承認され、第6期協議会は計116の個人・団体の体制で進めていくこととなりました。
最初に会長と会長代理の選任が行われ、会長に土屋委員、会長代理に吉田委員が再任されました。
土屋会長からは、短期目標のゴールが近付いている中、石西礁湖でどんな研究が行われてきたか、どのような結果が得られているのか、どのような成果が上げられ、どのような反省点を持っているか整理し、次の段階に進むべきとの挨拶がありました。
また、今回の協議会は2016年の夏季に発生したサンゴ白化現象に焦点をあてて意見交換するとの説明があり、議題に移りました。
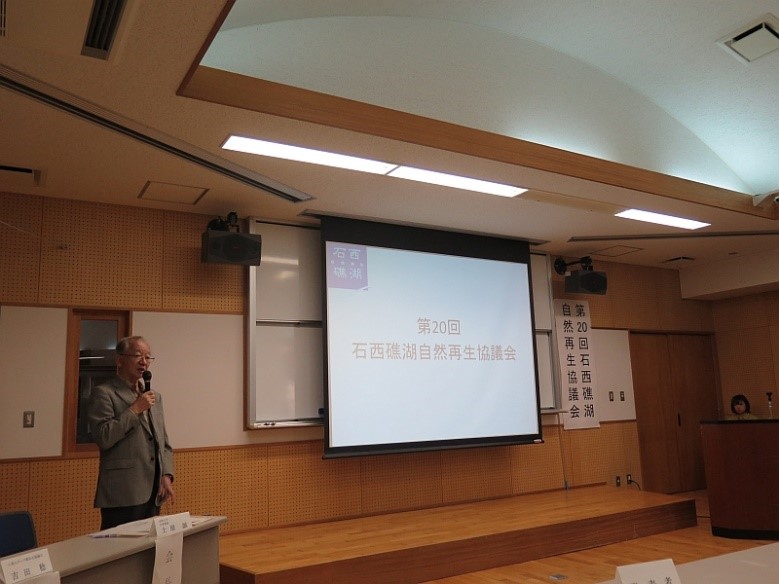 |
| 土屋会長の挨拶 |
1.石西礁湖自然再生事業の評価とデータ整理・利活用について
環境省より、協議会の展開すべき取組や短期目標の評価に活用するためのデータ解析、可視化についての紹介がありました。会場からは、評価にあたり取組の各実施主体から意見を集めるべきとの声があり、次の段階に進むために意見収集が必要であることが確認されました。
2.2016年の石西礁湖の大規模白化について
2016年の大規模白化に関する話題提供が6件ありました。
(1)2016年の白化状況について
環境省より、石西礁湖サンゴ群集モニタリング調査で実施したスポットチェック法による白化調査の結果が紹介されました。白化による死亡率が70.1%に至ったこと、高水温に曝された時間が短い場所では死亡率が低かったことなどが報告されました。
 |
| 伊藤委員(環境省石垣自然保護官事務所) |
(2)2016年の石西礁湖大規模白化現象におけるサンゴ種別差
琉球大学の中村委員より、環境省の石西礁湖サンゴ群集モニタリング調査で実施したサンゴ種別の白化調査の結果が報告されました。2016年の白化状況、前回の大規模白化があった2007年との比較、将来を見据えた対策などが紹介され、モニタリングが重要であるとの意見が述べられました。
 |
| 中村委員(琉球大学) |
(3)2016年の沖縄県周辺海域の高水温とその気象要因について
沖縄気象台の林委員より、2016年の高水温の気象要因について紹介がありました。2016年は気圧配置が特別で台風の動きが例年と異なっていたこと、2016年は深い層の水温まで高まっていたことなど、広域にわたる高水温の状況、形成メカニズムについて説明がありました。質疑では、地球温暖化の影響や高水温の予想の可能性に話が展開しました。
 |
| 林委員(沖縄気象台) |
(4)サンゴの病気と白化
静岡大学の鈴木委員より、サンゴの病気と白化に関する知見をご紹介いただきました。サンゴの白化は凝縮したり色が抜け落ちたりした共生藻類がサンゴに補食されて起きる現象で、活性酸素、バクテリア、ウイルスが関与していること、従来、表面が藻類に覆われたサンゴは死亡したと考えられてきましたが、これは白化防御機構の一つとも考えられていることといったご報告があり、サンゴの生理活性にかかわるモニタリングが必要との提言もありました。
 |
| 鈴木委員(静岡大学) |
(5)観光業(ダイビング業)から見たサンゴの白化現象による影響
石垣島マリンレジャー協同組合の屋良部代表理事より、2016年の大規模白化の影響について観光業の視点から報告がありました。サンゴが回復するまで時間がかかることが心配であること、レジャーダイバーによるサンゴの植え付け活動を進めていくことなどが紹介されました。
 |
| 屋良部氏(石垣島マリンレジャー協同組合代表理事) |
(6)魚がサンゴの回復に貢献する可能性について
西海区水産研究所の名波委員より、魚のサンゴの「かじりとり」行動により海藻やカイメン類が剥離され、サンゴの回復に貢献する可能性があることについて紹介がありました。また質疑を通じて、漁獲とサンゴの着生とのバランスを保つことが重要との意見が述べられました。
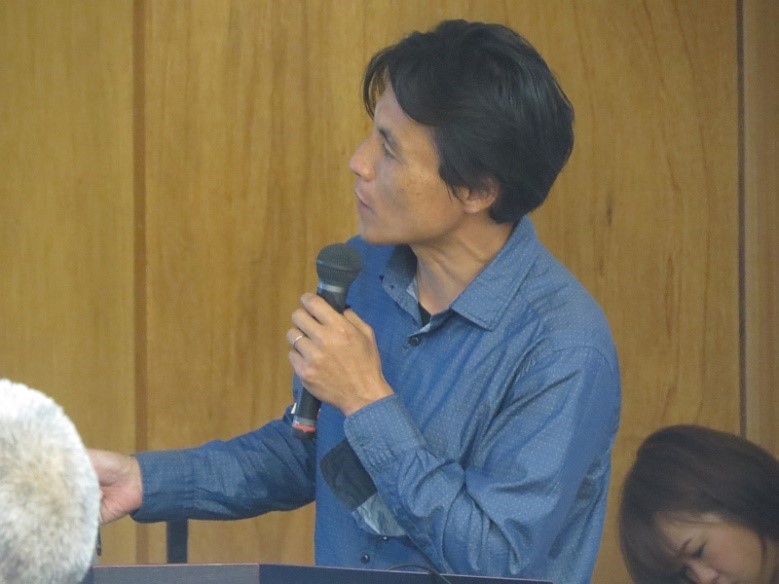 |
| 名波委員(西海区水産研究所亜熱帯研究センター) |
その後、2016年の白化に関する話題提供を通じたディスカッションが行われました。
吉田会長代理からは、白化や温暖化対策は一人ひとりが絶えずサンゴを守りたい、次の世代に残したいという感覚を持つことが重要との意見が述べられました。
WWFの鈴木委員からは、死んでしまった7割のサンゴを憂うよりも、残りの3割に何ができるかという姿勢が大事であるとの意見が出されました。
各話題提供者からは、普及啓発が重要であることや、新しいモニタリング方法の提案、地球温暖化の緩和、ダイバーに死滅したサンゴの様子を見せて知ってもらう取組み、漁業・観光業と調査研究との連携など、多岐にわたる意見が述べられました。
この他に、協議会の体制や開催回数を見直すべきであるとの意見が出されました。情報共有にとどまらず、グループディスカッションなど集中的な議論が必要との趣旨です。土屋会長から、事務局と意見交換し、来年度の協議会につなげていくとの考えが示されました。
3.その他
協議会の各WGと部会、石西礁湖サンゴ礁基金の活動報告は、資料配布の形式で行われました。
最後に、WWFの鈴木委員より、サンゴ礁を守るための認定制度作りについて説明がありました。
第20回 石西礁湖自然再生協議会
配布資料
|
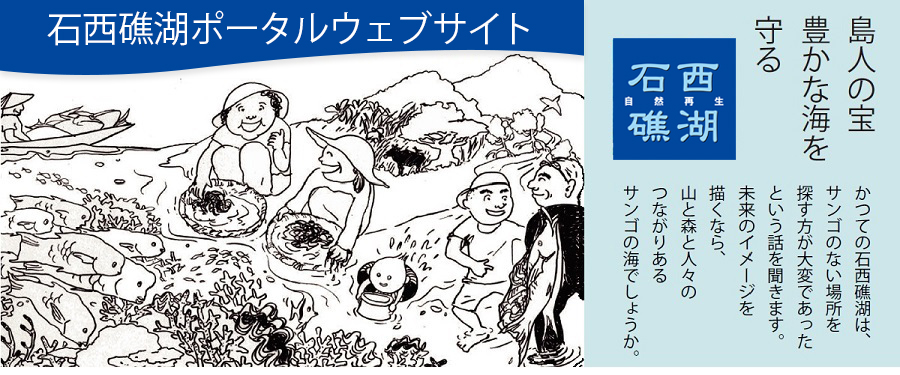

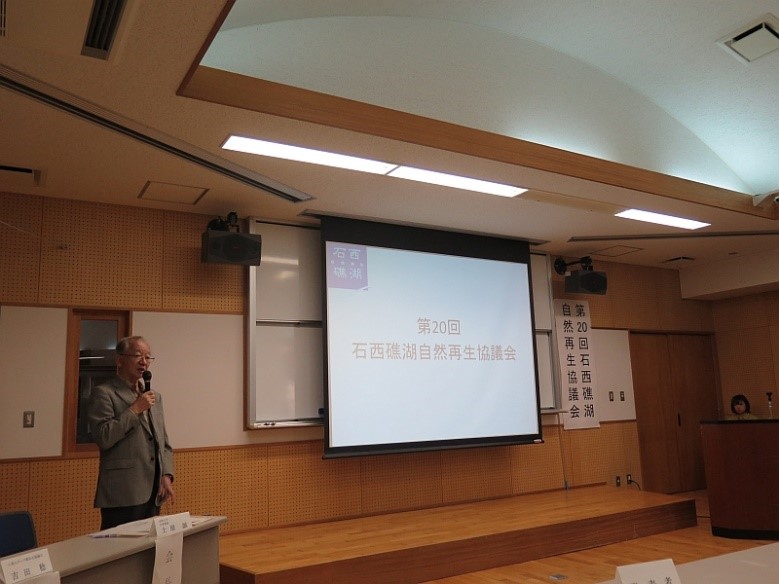





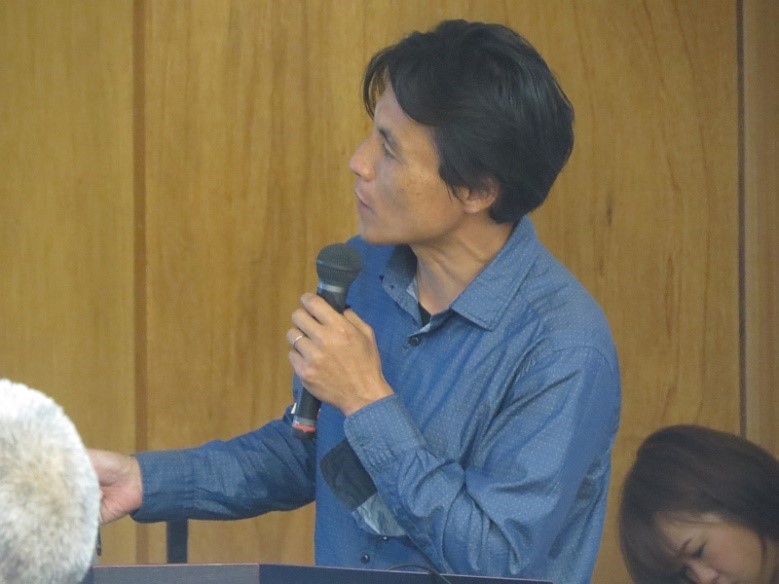
 第20回協議会議事次第
第20回協議会議事次第