‘و35‰ٌپ@گخگ¼ڈتŒخژ©‘Rچؤگ¶‹¦‹c‰ï‚ًٹJچأ‚µ‚ـ‚µ‚½
—كکa7”N3Œژ10“ْ‚ةپA‘و35‰ٌگخگ¼ڈتŒخژ©‘Rچؤگ¶‹¦‹c‰ï‚ھٹJچأ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پBŒآگlپA’c‘جپAچ‘‚â’n•û‚ج‹@ٹض‚ب‚ا‚جŒv46ˆدˆُ‚ھڈoگب‚µپA–T’®“™‚ًٹـ‚ك64–¼‚ھژQ‰ء‚µ‚ـ‚µ‚½پB
 |
| ‰ïڈê‚ج–ح—l |
‚PپDٹJ‰ï
پ@ٹآ‹«ڈب‰«“ꉂ”üژ©‘Rٹآ‹«ژ––±ڈٹ‚ج–k‹´ڈٹ’·پA“àٹt•{‰«“ê‘چچ‡ژ––±‹ا“ك”eچ`کpپE‹َچ`گ®”ُژ––±ڈٹ‚ج‹{—¢چ`کp‹َچ`‹Zڈp‘خچôٹ¯پA‹g“c‰ï’·‚و‚èٹJ‰ïˆ¥ژA‚ھ‚ ‚ء‚½پB
‚QپD‘و10ٹْگV‹KژQ‰ءˆدˆُ‚جڈذ‰î
پ@Œآگl2–¼پA’c‘جپE–@گl3’c‘ج‚ھگV‚½‚ةژQ‰ء‚ًٹَ–]‚µپAڈoگبˆدˆُ‚ج‰ك”¼گ”‚جژ^گ¬‚ة‚و‚èڈ³”F‚³‚ꂽپB
پ@پZŒآگlپFچrˆن ’‰چsژپپiˆê”تچà’c–@گlژ©ژ،‘جچ‘چغ‰»‹¦‰ïپj
پ@پ@پ@پ@پ@–k–ى —Tژqژپپiˆê”تچà’c–@گlژ©‘Rٹآ‹«Œ¤‹†ƒZƒ“ƒ^پ[پj
پ@پZ’c‘جپFUpsideچ‡“¯‰ïژذ
پ@پ@پ@پ@پ@ˆê”تژذ’c–@گlƒTƒXƒeƒiƒuƒ‹ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhگخٹ_
پ@پ@پ@پ@پ@ٹ”ژ®‰ïژذƒtƒWƒ^ ‹ZڈpƒZƒ“ƒ^پ[
‚RپD‹cژ–
پi‚Pپjژ‘±“IٹCˆو—ک—pƒڈپ[ƒLƒ“ƒOƒOƒ‹پ[ƒv‚جگف’u‚ة‚آ‚¢‚ؤ
پ@کaگٍˆدˆُ‚و‚èپuژ‘±“IٹCˆو—ک—pƒڈپ[ƒLƒ“ƒOƒOƒ‹پ[ƒvپv‚جگف’u‚ھ’ٌˆؤ‚³‚êپAڈoگبˆدˆُ‚ج‰ك”¼گ”‚جژ^گ¬‚ة‚و‚èڈ³”F‚³‚ꂽپB–{ƒڈپ[ƒLƒ“ƒOƒOƒ‹پ[ƒvپiˆب‰؛WGپj‚إ‚حپAچsگ‘gگDپAƒ}ƒٹƒ“ƒŒƒWƒƒپ[ژ–‹ئژز’c‘جپAٹدŒُ‹¦‰ï“™‚ھچ\گ¬—vˆُ‚ئ‚ب‚èپAگخگ¼ڈتŒخ‹y‚رژü•سٹCˆو‚إ‚جژ‘±“IٹCˆو—ک—p‚جژہŒ»‚ةŒü‚¯‚½ٹˆ“®‚ًچs‚¤پB“––ت‚جژه—v‚بژو‘g‚ئ‚µ‚ؤپAپuگخگ¼ڈتŒخژ©‘Rچؤگ¶‘S‘جچ\‘zچs“®Œv‰و2024–2028پv‚ة‚¨‚¯‚éڈd“_چ€–ع‚إ‚ ‚éپuگخگ¼ڈتŒخ‚ة‚¨‚¯‚éژ‘±‰آ”\‚بٹدŒُ—ک—pƒKƒCƒhƒ‰ƒCƒ“‚جچىگ¬‚ئٹˆ—pپv‚جگ„گi‚ًچs‚¤پB
‚SپD•ٌچگ
پi‚Pپjٹآ‹«ڈبژ©‘Rچؤگ¶ژ–‹ئ‚ج•ٌچگ
پEگخگ¼ڈتŒخƒTƒ“ƒSŒQڈWƒ‚ƒjƒ^ƒٹƒ“ƒO’²چ¸
پ@‚¢‚إ‚ ٹ”ژ®‰ïژذ‰«“êژxژذ‚جگخگXˆدˆُ‚و‚èپAٹآ‹«ڈب‚ھژہژ{‚·‚éگخگ¼ڈتŒخƒTƒ“ƒSŒQڈWƒ‚ƒjƒ^ƒٹƒ“ƒO’²چ¸Œ‹‰ت‹y‚رژQچlڈî•ٌ‚ئ‚µ‚ؤ’|•x“ىچqکH“™‚إ‚ج2024”N‚جƒTƒ“ƒS”’‰»ڈَ‹µ‚ھ•ٌچگ‚³‚ꂽپB2024”N‚جƒTƒ“ƒS”’‰»Œ»ڈغ‚ج‰e‹؟‚ةٹض‚·‚é‘O‰ٌ‹¦‹c‰ïŒم‚جŒ‹‰ت‚ئ‚µ‚ؤپA12Œژ‚جƒXƒ|ƒbƒgƒ`ƒFƒbƒN’²چ¸‚إ‚ح”’‰»—¦‚ھ65.5پ“پAژ€–S—¦‚ھ25.5پ“‚ئ‚ب‚èپA9Œژ’²چ¸ژ‚ئ”نٹr‚µ‚ؤƒTƒ“ƒS‚جژ€–S—¦‚ھ‘‰ء‚µ‚½پB‚»‚ج‘¼پAƒTƒ“ƒS’è’…—ت’²چ¸Œ‹‰ت‚ب‚ا‚ھ•ٌچگ‚³‚ꂽپBگخگ¼ڈتŒخ‚إ‚ح2022”NپA2024”N‚ئ‘ه‹K–ح”’‰»‚ھکA‘±‚µ‚ؤ‚¨‚èپAچ،Œم‚àگخگ¼ڈتŒخ‚جƒTƒ“ƒS‚ھ‰ٌ•œ‚·‚é‚©—\’f‚ً‹–‚³‚ب‚¢ڈَ‹µ‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پB
پEگخگ¼ڈتŒخƒTƒ“ƒSŒQڈWڈC•œژژŒ±
پ@ˆê”تچà’c–@گl‰«“ꌧٹآ‹«‰بٹwƒZƒ“ƒ^پ[‚ج‰ھ“cˆدˆُ‚و‚èپAٹآ‹«ڈب‚ھژہژ{‚·‚éگخگ¼ڈتŒخƒTƒ“ƒSŒQڈWڈC•œژژŒ±‚جگi’»ڈَ‹µ‚ھ•ٌچگ‚³‚ꂽپB–{ژ–‹ئ‚إ‚ح”’‰»Œ»ڈغ‚ب‚ا‚ج‘ه‹K–حٹh—گ‚ھ”گ¶‚µ‚ؤ‚àƒTƒ“ƒS‚ج‰ٌ•œ—ح‚ًˆغژ‚·‚邽‚ك‚ج‘خچô‚ئ‚µ‚ؤپA—cگ¶‹ں‹‹‹’“_‚جگ®”ُ‚âچ‚گ…‰·“K‰چô‚ب‚ا‚ًژژŒ±‚µ‚ؤ‚¢‚éپBچ،”N“xژہژ{‚µ‚½چ‚گ…‰·“K‰چô‚ئ‚µ‚ؤ‚جژصŒُژژŒ±‚إ‚حپAژصŒُ‚ة‚و‚è”’‰»‚جگiچs‚ھڈ‚ب‚¢’n“_‚ھŒ©‚ç‚ꂽپB‚ـ‚½پA7Œژڈمڈ{‚ةچèژ}کp‚جگ[ڈê‚ضˆع“®‚µ‚½ƒTƒ“ƒS‚حپA”’‰»‚ج‰e‹؟‚ً‚ظ‚ئ‚ٌ‚اژَ‚¯‚ب‚©‚ء‚½‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پB
پi‚Qپj•”‰ï‚جٹˆ“®•ٌچگ
پ@چ،”N“x‘و2‰ٌپi’تژZ‘و10‰ٌپj‚جٹCˆوپE—¤ˆو‘خچô•”‰ïپA•پ‹yŒ[”پE“Kگ³—ک—p•”‰ïپAٹwڈp’²چ¸•”‰ï‚ة‚آ‚¢‚ؤپAٹe•”‰ï’·‚و‚èٹˆ“®•ٌچگ‚ھچs‚ي‚ꂽپB
پ@—كکa7”N2Œژ19“ْ‚ةٹJچأ‚³‚ꂽٹCˆوپE—¤ˆو‘خچô•”‰ï‚إ‚حپA•”‰ï‚جٹˆ“®‚ةٹضکA‚·‚éˆدˆُ‚جژو‘g‚ج‹¤—L‚âپAٹآ‹«ڈبƒOƒٹپ[ƒ“ƒڈپ[ƒJپ[ژ–‹ئپA’|•x’¬‚ة‚¨‚¯‚éڈzٹآŒ^”_’{ژY‹ئ‚جگ„گi‚ةٹض‚·‚é•ٌچگ‚ھچs‚ي‚ꂽپBچs“®Œv‰و‚جڈd“_چ€–ع1پu—¤ˆو•‰‰×‚ج’لŒ¸پv‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپAگ¬‰تژw•W‚إ‚ ‚éپA
پ@‡@‰؛گ…“¹‚¨‚و‚رڈٍ‰»‘…‚جڈˆ—گlŒû‘‰ء
پ@‡AŒ—“à‚ج‘ح”ىگ¶ژY‚ئ—ک—p
‚ة‚آ‚¢‚ؤپAٹضŒW‹@ٹض‚جڈî•ٌ’ٌ‹ں‚ة‚و‚èƒxپ[ƒX‚ئ‚ب‚éگ”’l‚جژûڈWگ®—‚ھچs‚ي‚ꂽ‚±‚ئ‚ب‚ا‚ھ•ٌچگ‚³‚ꂽپB
پ@—كکa7”N2Œژ19“ْ‚ةٹJچأ‚³‚ꂽ•پ‹yŒ[”پE“Kگ³—ک—p•”‰ï‚إ‚حپA•”‰ï‚جٹˆ“®‚ةٹضکA‚·‚éˆدˆُ‚جژو‘g‚ج‹¤—L‚âپAپuژ‘±‰آ”\‚بƒ}ƒٹƒ“ƒŒƒWƒƒپ[•×‹‰ï in گخٹ_“‡پv‚جٹJچأ•ٌچگ‚ھچs‚ي‚ꂽپBچs“®Œv‰و‚جڈd“_چ€–ع2پuگخگ¼ڈتŒخ‚ة‚¨‚¯‚éژ‘±‰آ”\‚بٹدŒُ—ک—pƒKƒCƒhƒ‰ƒCƒ“‚جچىگ¬‚ئٹˆ—pپv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAƒKƒCƒhƒ‰ƒCƒ“چىگ¬‚جژه‘ج‚ئ‚ب‚éژ‘±“IٹCˆو—ک—pWG‚ھ—§‚؟ڈم‚°—\’è‚إ‚ ‚èپAژں”N“x‚ةƒKƒCƒhƒ‰ƒCƒ“چœژqˆؤ‚ًچىگ¬‚·‚éŒv‰و‚ئ‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پBڈd“_چ€–ع3پu”ھڈdژR’nˆو‚جژq‚ا‚à‚½‚؟‚ض‚جƒTƒ“ƒSٹwڈK‚جگ„گiپv‚ة‚آ‚¢‚ؤ‚حپAچ،”N“x‚جƒTƒ“ƒSٹwڈKژہژ{ڈَ‹µ‚ب‚ا‚ھگ¬‰ت‚ئ‚µ‚ؤ•ٌچگ‚³‚êپAژں”N“x‚حƒTƒ“ƒSٹwڈKژہژ{چZ‚âچuژtˆçگ¬‚ًگ„گi‚·‚é‚ئ‚ئ‚à‚ةپAٹù‘¶‚جٹC—mٹwڈK“™‚ةƒTƒ“ƒSٹwڈK‚ج—v‘f‚ًژو‚è“ü‚ê‚éƒTƒ|پ[ƒg‚ًچs‚ء‚ؤ‚¢‚Œv‰و‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پB
پ@—كکa7”N2Œژ20“ْ‚ةٹJچأ‚³‚ꂽٹwڈp’²چ¸•”‰ï‚إ‚حپA•”‰ï‚جٹˆ“®‚ةٹضکA‚·‚éˆدˆُ‚جژو‘g‚ج‹¤—L‚âپAژ©‘Rچؤگ¶ژ–‹ئ‚إ‚ ‚éگخگ¼ڈتŒخƒTƒ“ƒSŒQڈWƒ‚ƒjƒ^ƒٹƒ“ƒO’²چ¸‚âگخگ¼ڈتŒخƒTƒ“ƒSŒQڈWڈC•œژژŒ±‚جژہژ{Œ‹‰ت‚ةٹض‚·‚é•ٌچگ‚ھچs‚ي‚ꂽپB‚ـ‚½پAڈd“_چ€–ع‚جگi’»‚ةٹض‚·‚éڈî•ٌ‹¤—L‚ئ‹cک_‚ھچs‚ي‚ꂽپB—كکa6”N12Œژ17“ْ‚ةٹJچأ‚³‚ꂽٹwڈp’²چ¸•”‰ïچى‹ئƒ`پ[ƒ€‚إ‚حپAگخگ¼ڈتŒخƒTƒ“ƒSŒQڈWƒ‚ƒjƒ^ƒٹƒ“ƒO’²چ¸‚إ“¾‚ç‚ꂽƒfپ[ƒ^‚ج‰ًگح‚ة‚آ‚¢‚ؤ‹cک_‚ھچs‚ي‚ꂽپBچ،Œم‚ج—Dگو“I‚بŒں“¢ƒeپ[ƒ}‚ئ‚µ‚ؤپAƒTƒ“ƒS”’‰»‚ھ‹N‚±‚è‚â‚·‚¢ڈêڈٹ‚ج“ء’èپA‘ه‹K–حٹh—گ‚©‚ç‰ٌ•œ‚µ‚â‚·‚¢ٹCˆو‚ئ‚µ‚ة‚‚¢ٹCˆو‚ج’ٹڈoپAگخگ¼ڈتŒخ‚جƒTƒ“ƒS‚جژي‘½—lگ«‚ج•د‰»‚ھ‹“‚°‚ç‚ꂽپB
پi‚Rپjƒڈپ[ƒLƒ“ƒOƒOƒ‹پ[ƒv‚جٹˆ“®•ٌچگ
پE‚è‚‚ئ‚¤‚فWG
پ@ˆہŒ³چ„ˆدˆُپi–k—¢‘هٹwپj‚و‚èپA—كکa7”N3Œژ7“ْ‚ةٹJچأ‚³‚ꂽچ،”N“x‘و2‰ٌ‚جپu—¤‚ئٹC‚ج‚آ‚ب‚ھ‚èWGپv‚جٹˆ“®•ٌچگ‚ھچs‚ي‚ꂽپBWG‚ة‚ح–ٌ50–¼‚ھژQ‰ء‚µپAٹضگS‚جچ‚‚³‚ھژf‚ي‚ꂽپBWG‚إ‚ح6–¼‚جŒ¤‹†ژز‚و‚èپAگخگ¼ڈتŒخ‚ج—¤ˆو•‰‰×‚ئƒTƒ“ƒSڈت•غ‘S‚ةٹضکA‚·‚éچإگV‚جŒ¤‹†‚âژو‘g‚ھ•ٌچگ‚³‚ꂽپB
پ@WG‚جٹˆ“®•ٌچگ‚ئٹضکA‚µپAˆہŒ³چ„ˆدˆُ‚ة‚و‚é’êژ؟ƒٹƒ“‚ةٹض‚·‚錤‹†“à—e‚ھڈذ‰î‚³‚ꂽپB’êژ؟ƒٹƒ“‚ھ’¼گعƒTƒ“ƒS‚ة—^‚¦‚é‰e‹؟‚ة‰ء‚¦پA’êژ؟‚ج”÷گ¶•¨‘w‚ً•د‰»‚³‚¹‚邱‚ئ‚ة‚و‚éƒTƒ“ƒS‚ض‚ج‰e‹؟‚ھ–¾‚ç‚©‚ة‚ب‚è‚آ‚آ‚ ‚é‚ئ‚ج‚±‚ئ‚إ‚ ‚ء‚½پB
پi‚Sپjˆدˆُ‚جژو‘g•ٌچگ‚¨‚و‚رکb‘è’ٌ‹ں
پEˆدˆُ‚جٹˆ“®•ٌچگپiژو‘g‹¤—LƒVپ[ƒgپj
پ@ژ––±‹ا‚و‚èپAˆدˆُ‚و‚è’ٌڈo‚³‚ꂽچ،”N“x‚جٹˆ“®•ٌچگپiژو‘g‹¤—LƒVپ[ƒgپj‚ة‚آ‚¢‚ؤ•ٌچگ‚ھ‚ ‚ء‚½پB30ˆدˆُ‚و‚è•ٌچگ‚ھ‚ ‚èپA•ٌچگ“à—e‚حڈd“_چ€–ع‚جگi’»•ٌچگ“™‚ةٹˆ—p‚³‚ꂽپBˆدˆُ‚جژو‘g‚ً’m‚邱‚ئ‚إچ،Œم‚جکAŒg‚ج‚«‚ء‚©‚¯‚ئ‚ب‚邱‚ئ‚ھٹْ‘ز‚³‚ê‚éپB
پEگخٹ_ژsƒTƒ“ƒS•غ‘S’،“àکAŒgƒ`پ[ƒ€‚جٹˆ“®•ٌچگ
پ@گخٹ_ژsٹآ‹«‰غ‚جڈم’nˆدˆُ‚و‚èپAگخٹ_ژsƒTƒ“ƒS•غ‘S’،“àکAŒgƒ`پ[ƒ€‚جٹˆ“®‚ھ•ٌچگ‚³‚ꂽپBƒTƒ“ƒS•غ‘SٹضŒWژزŒ¤ڈC‚ب‚ا‚جŒ»ڈêژ‹ژ@پA‘½گ”‚جٹضŒW’c‘ج‚ئ‚جˆسŒ©Œًٹ·پAƒTƒ“ƒSڈت•غ‘S‚ة‚آ‚ب‚ھ‚é’،“à‰،’fژ{چô‚ئ‚µ‚ؤ‚ج‹xچk“cٹˆ—pƒvƒچƒWƒFƒNƒg‚ج’ٌˆؤ‚ب‚ا‚ھچs‚ي‚ꂽپB
پE‘و‚S‰ٌ‚â‚¢‚ـSDGs ƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€‚جٹJچأ•ٌچگ
پ@”ھڈdژRƒچپ[ƒJƒ‹SDGsگ„گi‹¦‹c‰ï‚ج“،–{ژپ‚¨‚و‚ر“––ءژپ‚و‚èپA2024”N11Œژ‚ةٹJچأ‚³‚ꂽپu‘و4‰ٌ ƒJپ[ƒvƒŒƒ~ƒAپ~‚â‚¢‚ـSDGsƒVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€پv‚جٹJچأٹT—v‚ھ•ٌچگ‚³‚ꂽپBچ‡‚ي‚¹‚ؤپA“ْ–{DAO–@‚ًٹˆ—p‚µپAƒTƒ“ƒSڈت•غ‘S‚ً‰؟’l‚ئ‚·‚é”ھڈdژR‚إ‚ج’nˆوڈzٹآ‹¤گ¶Œ—‚أ‚‚è‚جچ\‘z‚ئƒAƒvƒٹپhaniMaپh‚ھڈذ‰î‚³‚ꂽپB
‚TپD“ء•تچu‰‰
پu‘fگ°‚炵‚¢ƒTƒ“ƒSڈت‚ً–¢—ˆ‚ضپv “y‰® گ½ژپپiگخگ¼ڈتŒخژ©‘Rچؤگ¶‹¦‹c‰ï‘O‰ï’·پj
پ@–{‹¦‹c‰ï‚جڈ‰‘م‰ï’·‚ئ‚µ‚ؤپA2006”N‚و‚è18”Nٹش‚ة“n‚è‰ï’·گE‚ً–±‚ك‚ç‚ꂽ“y‰®ژپ‚و‚èپA–{‹¦‹c‰ï‚جڈ«—ˆ‚ضŒü‚¯‚½ƒپƒbƒZپ[ƒW‚ئ‚µ‚ؤ“ء•تچu‰‰‚ً‚¢‚½‚¾‚¢‚½پB
پ@چu‰‰‚إ‚حپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚ج‹¦‹c‰ï‚ج•à‚ف‚ئ‚µ‚ؤپAڈ‰ٹْ‚جˆسŒ©Œًٹ·‚جڈَ‹µپA‚±‚ê‚ـ‚إ‚ةچô’肳‚ꂽŒv‰و‚âگخگ¼ڈتŒخ‚جŒ»ڈَ‚ً“`‚¦‚éچûژq“™پA2016پ`2017”N‚ةچs‚ي‚ꂽژو‚è‚ـ‚ئ‚ك‚ب‚ا‚ھڈذ‰î‚³‚ꂽپB‹¦‹c‰ï‚جŒ»ڈَ‚ئ‚µ‚ؤپAگف—§“–ڈ‰‚حژلژè‚ج‹™‹ئژز‚ئˆسŒ©Œًٹ·‚ً‚µ‚ؤ‚«‚½‚ھپAچإ‹ك‚ح‚»‚ج‚و‚¤‚ب‹@‰ï‚ھ“¾‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢‚±‚ئ‚ب‚ا‚ض‚جژw“E‚ھ‚ب‚³‚ꂽپB‹¦‹c‰ï‚جچ،Œم‚ة‘خ‚µپAˆب‰؛‚ج3‚آ‚ج’ٌŒ¾‚ھ‚ ‚ء‚½پB
پ@‡@‚و‚èچL‚¢ڈî•ٌ”گM‚ئ‹Lک^ڈW‚ًچىگ¬‚·‚é
پ@‡A‚±‚ê‚ـ‚إ‚ج‹cک_‚ً‘چچ‡‰ًگح‚µپAچؤگ¶‚ج‚½‚ك‚ج“¹‹ط‚ً—§‚ؤژہ‘H‚·‚é
پ@‡BƒTƒ“ƒSڈت‚ج•غ‘Sٹˆ“®‚ًگخگ¼ڈتŒخ‚©‚çگ¢ٹE‚ض”گM‚µپA’n‹…ٹآ‹«‚ج•غ‘S‚ةچvŒ£‚·‚é
 |
| “y‰®‘O‰ï’·‚ج“ء•تچu‰‰ |
پ@پ@پ@چu‰‰ŒمپA‹g“c‰ï’·‚و‚肱‚ê‚ـ‚إ‚ج‚²چvŒ£‚ض‚جٹ´ژسڈَ‚ھ‘،‚ç‚ꂽپB
 |
| ٹ´ژسڈَ‚ج‘،’و |
‚UپD•آ‰ï
پ@’†‘؛•›‰ï’·‚©‚ç•آ‰ï‚جˆ¥ژA‚ھ‚ ‚ء‚½پB
”z•zژ‘—؟
|
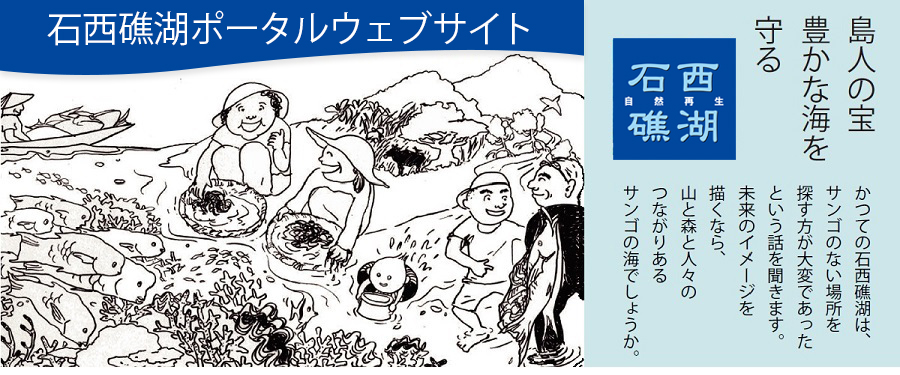



 ‹cژ–ژں‘وپAژ‘—؟ˆê——
‹cژ–ژں‘وپAژ‘—؟ˆê——