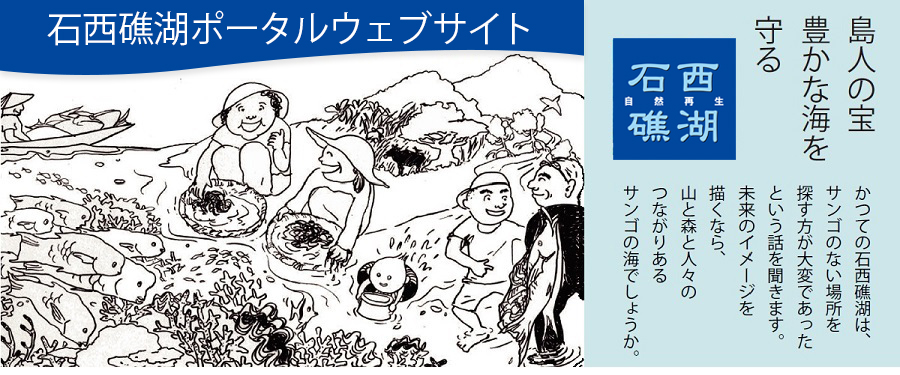|
石西礁湖生きもの図鑑ー貝のなかま |
|

|
種名:ウミウサギガイ 学名:Ovula ovum 殻長10cm程度。 光沢のある白色の貝殻が特徴だが、海中では黒色の外套膜で覆われている。サンゴ礁や岩礁のソフトコーラルが群生している岩場にいることが多く、ソフトコーラルを食べる。貝殻が市場で流通しており、アクセサリーに加工される他、収集家に人気がある。 |

|
種名:シロレイシガイダマシ 学名:Drupella fragum 殻長3cm程度。 サンゴの枝の間にいることが多く、サンゴ捕食者として有名である。サンゴに張り付いた本種は、サンゴに消化液を吐いて、歯舌と呼ばれる特殊な歯で軟組織を剥いで食べる。沖縄県だけでなく和歌山県以南の日本各地で大発生する時があり、サンゴの食害をもたらす生物としてオニヒトデと共に駆除対象となっている。駆除された貝は廃棄されていたが、ここ近年貝殻を加工してアクセサリーなどにするなどして利用され始めている。また、自然界でもサンゴヤドカリ類の宿として利用されている。 |


|
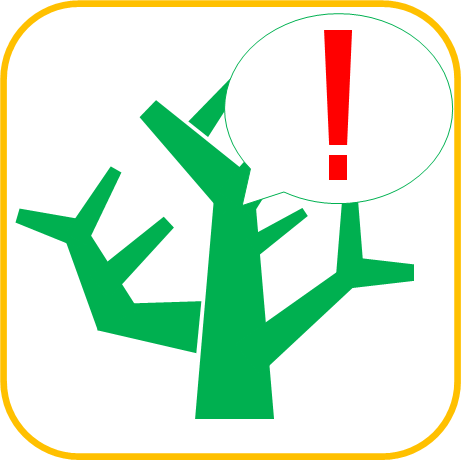 有害生物
有害生物
|

|
種名:シロレイシガイダマシ 学名:Drupella fragum サンゴを集団で捕食している様子。 殻長3cm程度。 サンゴの枝の間にいることが多く、サンゴ捕食者として有名である。サンゴに張り付いた本種は、サンゴに消化液を吐いて、歯舌と呼ばれる特殊な歯で軟組織を剥いで食べる。沖縄県だけでなく和歌山県以南の日本各地で大発生する時があり、サンゴの食害をもたらす生物としてオニヒトデと共に駆除対象となっている。駆除された貝は廃棄されていたが、ここ近年貝殻を加工してアクセサリーなどにするなどして利用され始めている。また、自然界でもサンゴヤドカリ類の宿として利用されている。 |


|
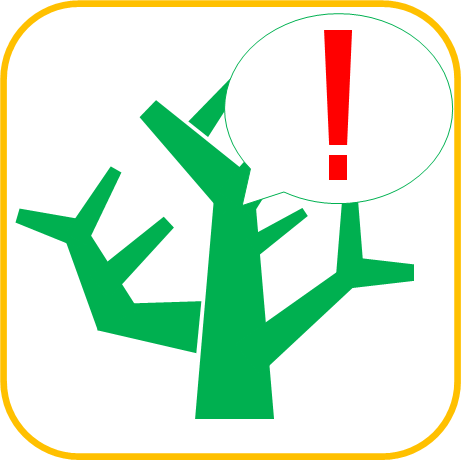 有害生物
有害生物
|

|
種名:ハナミドリガイ 学名:Thuridilla splendens 全長3cm程度。 深緑から緑色の体色に輪郭のぼやけた白色斑が入り、触角の先端が赤からオレンジ色であることが特徴。サンゴ礁の岩の上や砂地などいたるところに生息している。「〜ガイ」と名前が付いているが、ウミウシなかまは巻き貝に含まれる為、本種を含めしばしばこのような名前が付くことがある。よくダイバーの写真対象となる。 海藻を主に食べると言われている。 |

|
種名:サキシマミノウミウシ 学名:Samla takashigei 全長3cm程度。 青白い体色と、先端下がオレンジ色の突起が多数背中から生えていることが特徴。サンゴ礁の岩の上や岩・サンゴの隙間でよく見られる。名前に「サキシマ」と入っているが、日本で最初に報告されたのが先島諸島の石垣島であったことに由来している為と言われている。背中の突起などの特徴的な見た目から、ダイバーに人気がある。 ヒドロ虫を主に食べていると言われるが、明確には分かっていない。 |

|
種名:フリエリイボウミウシ 学名:Phyllidia picta 全長4cm程度。 黒色の体色に先端が黄色の青灰色のイボ状の突起が特徴。体はウミウシのなかま中では硬い。サンゴ礁の岩の上や裏側でごく普通に見られる。ダイバーの写真対象となる。 海綿を主に食べている。 |

|
種名:シライトウミウシ 学名:Chromodoris magnifica 全長6cm程度。 外套膜の外側から順に、白色の細い色帯、太い黄色からオレンジ色の色帯と、体の中央に走る3本の黒から紺色の線、オレンジ色の触角、二次鰓が特徴。サンゴ礁の岩の上や裏側でごく普通に見られるが、見た目が類似している種が複数種いる為、間違えることも多い。ダイバーに人気のあるウミウシのひとつである。 海綿を主に食べている。 |

|
種名:ミドリリュウグウウミウシ 学名:Tambja morosa 全長8cm程度。 黒から深緑色の体色に、頭部の縁が青色であることが特徴。また、リュウグウウミウシのなかま独特の二次鰓の形も特徴である。サンゴ礁の岩の上や岩礁付近の砂地、海藻の上などいたるところで見られる。よくダイバーの写真対象となる。 コケムシを主に食べている。また、イシガキリュウグウウミウシによく捕食される姿も目撃されている。 |

|
種名:シラナミガイ 学名:Tridacna maxima 殻長25cm程度。 波打った貝殻の口と殻の鱗状の複数の突起が特徴。サンゴ礁の岩やサンゴに穴をあけて生息しており、成長するにつれて岩から殻がはみ出る。挟む力が非常に強く貝殻も鋭い為、挟まれたり手などを切らないように注意すること。沖縄を中心に食用として出回っており、高値で取引されている。 小さいプランクトンや海中の浮遊物を吸い込んで食べることもあるが、主に外套膜に共生している褐虫藻と呼ばれる藻類から光合成によって生産された栄養を得ている。共生している褐虫藻は、シラナミガイの排出物を栄養としている。 |
 水産資源 |
|

|
種名:コブシメ 学名:Sepia latimanus 外套長(ヒレの先端から胴体の付け根の長さ)40cm程度。 本種を含むコウイカのなかまの特徴として、胴体が太く、腕足が短い。本種は胴体に白点が散在し、ヒレや腕に横縞が走る。サンゴ礁のサンゴや岩場に生息し、単独または群れで遊泳する。冬から春先の産卵期になると、ユビエダハマサンゴなどのイシサンゴのなかまの隙間にピンポン玉の様な卵を産み付け、卵を守るようにペアで周囲を警戒しながら泳ぐ。沖縄ではアオリイカと並び、高級食材として流通している。墨を利用した汁物が有名。釣り対象としてもメジャーであり、本種を狙った釣りも行われている。 主に魚や甲殻類を食べる。 |


|
 水産資源 |

|
種名:コブシメ 学名:Sepia latimanus 卵。外套長(ヒレの先端から胴体の付け根の長さ)40cm程度。 本種を含むコウイカのなかまの特徴として、胴体が太く、腕足が短い。本種は胴体に白点が散在し、ヒレや腕に横縞が走る。サンゴ礁のサンゴや岩場に生息し、単独または群れで遊泳する。冬から春先の産卵期になると、ユビエダハマサンゴなどのイシサンゴのなかまの隙間にピンポン玉の様な卵を産み付け、卵を守るようにペアで周囲を警戒しながら泳ぐ。沖縄ではアオリイカと並び、高級食材として流通している。墨を利用した汁物が有名。釣り対象としてもメジャーであり、本種を狙った釣りも行われている。 主に魚や甲殻類を食べる。 |


|
 水産資源 |

|
種名:マダコ科の1種 学名:Octopodidae gen sp. 擬態している様子。 全長100cm程度。 サンゴ礁や岩礁地帯の岩の隙間にてみられることがある。体色を自在に変化させることがよく知られており、敵から逃げる際などに周りの岩場に合わせてカモフラージュする。体に骨がなく柔らかい為、細く小さい穴の隙間に逃げ込むことが出来る。このように見た目が自在に変化し、体の大半を岩の隙間に隠していることが多い上、種間の違いが吸盤の形や数で判別されることが多い為、野外で見つけた際の同定は非常に難しい。沖縄では重要な水産資源で食用として市場を流通しており、漁業権が設定されている。 主に魚を食べる。 |


|
 水産資源 |

|
種名:マダコ科の1種 学名:Octopodidae gen sp. 全長100cm程度。 サンゴ礁や岩礁地帯の岩の隙間にてみられることがある。体色を自在に変化させることがよく知られており、敵から逃げる際などに周りの岩場に合わせてカモフラージュする。体に骨がなく柔らかい為、細く小さい穴の隙間に逃げ込むことが出来る。このように見た目が自在に変化し、体の大半を岩の隙間に隠していることが多い上、種間の違いが吸盤の形や数で判別されることが多い為、野外で見つけた際の同定は非常に難しい。沖縄では重要な水産資源で食用として市場を流通しており、漁業権が設定されている。 主に魚を食べる。 |


|
 水産資源 |