|
|
調査結果(FLASH)
調査結果(HTML)
石西礁湖の自然の状況を把握し、どのような自然再生が必要とされ、
またどのような方法で自然再生事業を実施するのが良いかを検討するために、
さまざまな調査を行いました。
調べたこと
- 石西礁湖地域の自然や社会の概況
石西礁湖内の島々の概要、気象、八重山の貴重な植物・動物、人口の推移、産業、観光業の動向などについて
- 自然環境はどんな状況か
石西礁湖内の潮の流れ、サンゴ礁、海草、マングローブなどの生息状況や、赤土、オニヒトデ、白化などサンゴ礁を破壊する要因の影響について
- どのように利用されているか
漁業、観光業による利用状況について
- どのような自然の保全・再生の方法があるか
サンゴの移植などの方法について
これまでに実施された調査から得られた主な結果を、ご紹介しましょう。
- 石西礁湖内の潮の動きについて
石西礁湖内での海水の流れ方を把握することは、赤土、サンゴの卵、オニヒトデの卵などがどこに流れ着くのかを考えるうえで重要な情報です。海水の流れは、潮の満ち引き(潮汐)、海底の地形、海上を吹く風の方向、八重山の北側を流れる黒潮の影響、海水の温度差などさまざまな要素によって決まります。
石西礁湖で実際に流れの方向を調べた結果が図**です。

石西礁湖内の海水の流れや、海水温を決める諸条件を入力し、コンピュータ上で流れの状況をシミュレーションするといった調査も行いました。その結果、海水温が上がりやすく冷めにくい海域などを推測することができ、これらの海域ではサンゴが白化する危険性が高いことが推測できます。
このような海水の流れに関する情報も参考にして、守るべき海域、サンゴの修復が必要な海域などを検討しました。

- サンゴ礁の状態について
石西礁湖では1983年から約100地点でサンゴの被度(一定面積の中でサンゴが覆っている割合)などを毎年観測しています。同じ地点で観測しているので調査結果を並べてみるとサンゴの健康状態を被度の変化からある程度捉えることが出来ます。
例えば、調査地点全体の被度を石西礁湖全体で集計してみると、図**のようになります。
1983年に大発生したオニヒトデによる食害でサンゴが大量に死滅した様子や、1989年の高水温による白化でも大量にサンゴが死滅した様子が読みとれます。
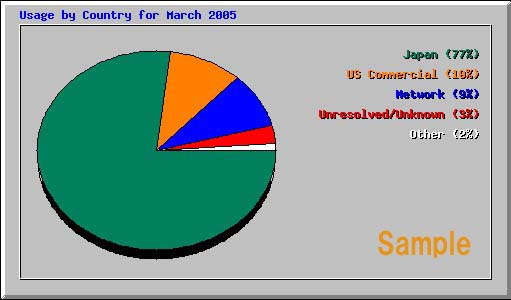
- オニヒトデの発生状況について
1993年から2001年までの石西礁湖モニタリングでの全地点平均生存サンゴ被度の変化
石西礁湖内でオニヒトデの分布調査(2003年7月〜8月、2004年2月)を行いました。
その結果、たくさんのオニヒトデが見られたところでは駆除(2003年10月、2004年2月)を行いました。
調査の結果確認されたオニヒトデの分布は、例えば2003年7月〜8月では次の図のようになり、
2004年の調査でもほぼ同様の海域で急増していることがわかりました。
目立って多くのオニヒトデが確認された場所は、次の8海域です。
- 竹富島南(竹富島の約2km南)
- マルグー周辺(竹富島の約4km南西)
- カナラグチ周辺(石垣島の登野城漁港の約2km南)
- テンマカケジュ周辺(石垣島の約4km南)
- ユイサーグチ周辺(石垣島の約6km南)
- 旧新里航路周辺(黒島の約1km北)
- スーハヤーグチ周辺(小浜島の約2km南)
- 名蔵湾(湾内)
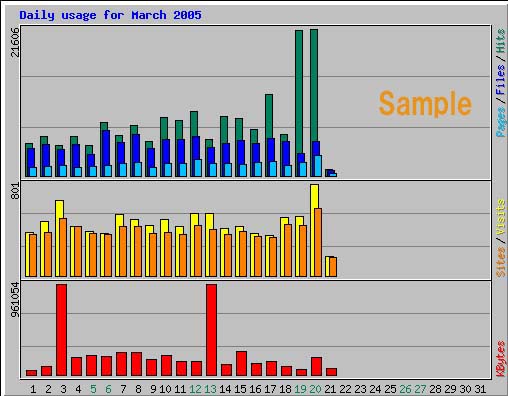
平成15年度オニヒトデ分布調査結果
- 漁業による利用状況について
石西礁湖では、追い込み網漁、カゴ網漁、小型定置網漁、刺し網漁、電灯潜り漁、
採貝漁などさまざまな漁業が行われています。
図**では八重山海域で水揚げされた漁獲量の推移をしめしました。
全体の漁獲量を見ると、70年代から80年代中頃にかけて急激に漁獲量が減少しましたが、
これは主に沖合でのカツオの漁獲量が減少したことによるものと考えられます。
サンゴ礁域での漁獲量も徐々に減少してきているのが解ります。

図**は、石西礁湖内での漁業利用調査のうち、漁場の位置を調べた結果です。
沿岸のサンゴ礁域のほとんどが、漁場としても重要な場所であることがわかります。
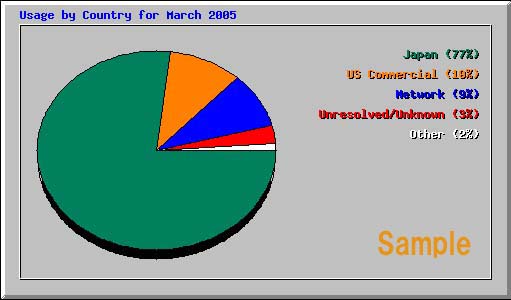
- 観光による利用状況について
石西礁湖を含む八重山地域には、年間61万人もの観光客が訪れます(平成14年度統計)。
石垣島から周辺離島を訪れ、竹富島のように伝統的な集落景観を楽しんだり、
西表島のような豊かな自然など、八重山には観光としてのアトラクションがたくさんありますが、
スキューバダイビングなど海洋を利用したスポーツを目的とした観光客もたくさん訪れます。
図**は、石西礁湖でスキューバダイビングに利用されているポイントを示しています。

- サンゴ礁を再生するための手法について
かつてサンゴ礁があった海域で、現在、何らかの原因で死滅したり衰退してしまった場所が
確認されています。
そのような海域のサンゴ礁を再生するために、どのような手法が有効かを調べる目的で
様々な試験を行いました。
これまではサンゴ群体の一部を採取し別の基盤に張り付ける方法が一般的でしたが、
現在では採取元となるサンゴへの影響を考慮し、有性生殖後の卵を基盤に
定着させるさまざまな手法が研究されています。
本調査では、岡本・野島(2003)が開発したサンゴ着生具(図参照)を用いた試験など、
具体的な再生修復につががる調査を実施しました。この着生具は、着生具のし易さや、
表面に生育したサンゴ群体を実際に自然の岩盤に固定するときの作業のし易さまで考慮
して開発されたものです。
現在は、実際に海中に設置した場合に、サンゴがどの程度着生するかを調べています。

サンゴの着生と加入の状況
自然下でどの程度のサンゴが着生し、それが翌年も生き残っているかを知ることは、サンゴの移植などにより修復すべき海域を検討するための情報として重要です。図**は、着生板とよばれる陶製の板をサンゴの産卵前に沈め、産卵後どのくらいのサンゴが付着したかを調べた結果です。
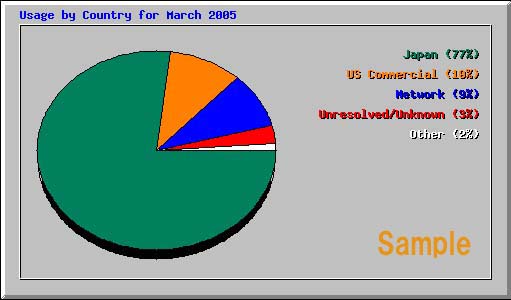
なお、石西礁湖自然再生調査報告書の内容は、PDFでご覧になれます。
|
|

