|
|
|
|
|
わが国の自然再生...自然再生推進法に基づいて実施 |
|
|
現在わが国における自然再生は、2002年12月に成立した「自然再生推進法」に基づいています。この法律の目的は、自然再生に関する施策を総合的に推進し、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することです。この法律は、平成15年1月1日より施行されています。
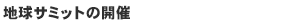
1992年のブラジルのリオデジャネイロで開催された地球サミットでは、気候変動枠組み条約(*1)とともに、「生物多様性条約」が採択されました。これは、生物の絶滅と生き物豊かな森林や湿原等の喪失を防ぎ、自然の恵持続的に利用できるようにするための条約です。現在190ヶ国近い国がこの条約に加わり、それぞれが自国の生物多様性保全の義務を負っています。条約第6条中では、国をあげてこれに取り組むための方針と計画、つまり「国家戦略」の作成が求められています。
*1)1992年の国連環境開発会議(UNCED)で155カ国によって署名された条約で、温室効果ガスの濃度を安定化させるために、締約国の一般政策目標とその実現のための枠組みを定めたもの。正式名称は「気候変動に関する国際連合枠組条約」。具体的な規制措置などは後の議論に委ねられた。

サミット開催以降、わが国においても1993年、「環境基本法」制定や、「生物多様性条約」の締結、「生物多様性国家戦略」策定等が進み、環境保全や持続可能な発展の考え方を基本においた施策が重視されるようになりました。そして「河川法」の改正、「食料・農業・農村基本法」等においても自然環境保全に関する施策が盛り込まれました。
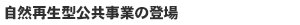
2001年5月、小泉総理大臣が就任する際の所信表明の中に、「21世紀に生きる子孫へ、恵み豊かな環境を確実に引き継ぎ、自然との共生が可能となる社会を実現したい」という表現が盛り込まれました。これを受けて同7月、総理主宰の「21世紀『環の国』づくり会議」方向において、「衰弱しつつあるわが国の自然生態系を健全なものに蘇らせていくためには、環境の視点からこれまでの事業・施策を見直す一方、順応的管理の手法を取り入れて積極的に自然を再生する公共事業、すなわち『自然再生型公共事業』を、都市と農産漁村のそれぞれにて推進することが必要」と提言され、「自然再生型公共事業」の文言が登場しました。また同12月には、総合規制改革会議「規制改革の推進に関する第1次答申」において、「海岸・浅海域等の水系域や都市域など既に自然の消失、劣化が進んだ地域では自然の再生や修復が重要な課題である。自然の再生、修復の有力な手法の一つに、地域住民、NPO等多様な主体の参画による自然再生事業があり、各省庁間の連携・役割分担の調整や関係省庁による共同事業実施など、省庁の枠を超えて自然再生を効果的・効率的に推進するための条件整備が必要」とされ、自然再生事業の位置付けとその進め方が示されました。
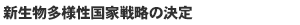
2002年3月には、従来の「生物多様性国家戦略」の見直しを行い「新生物多様性国家戦略」が決定されました。新戦略では、現在の自然環境が直面している3つの危機を指摘し、それに対して今後政府が目指すべき施策の大きな方向を示しました。それは、「保全の強化」、「自然再生」、「持続可能な利用」の3つです。危機及び、それに対する施策の方向の詳細を以下に示します。3つの大きな方向のうち、「自然再生」について、その具体策である「自然再生事業」の推進が規定されました。
これをうけて、2002年12月に「自然再生推進法」が成立し、2003年1月1日より施行され、釧路湿原をはじめとして、各地で自然再生事業がスタートしました。 |

